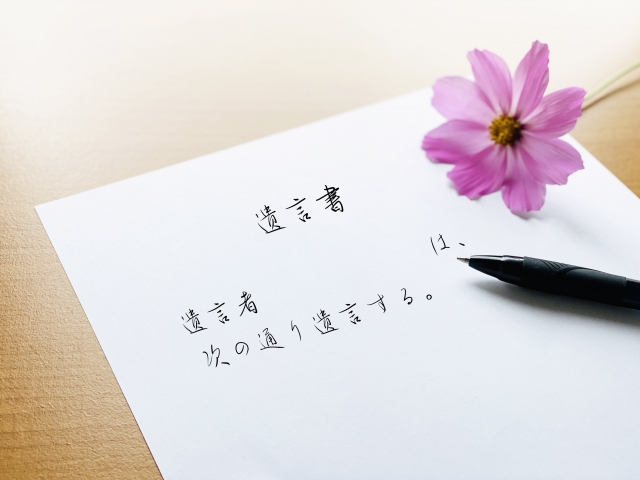皆さんこんにちは、司法書士の関良太です。
ご家族の事情はさまざまで親族関係は実に多彩です。
その中でも、どうしてもご自身の財産を相続人に相続させたくないと思っている方が一定数いらっしゃるようですので、相続させたくない人がいる場合にどうすれば良いか記事にします。
①廃除請求する
「廃除」とは民法892条を根拠とした相続権を持っている人を相続人から外す手続きです。
(推定相続人の廃除)
第八百九十二条
遺留分を有する推定相続人(相続が開始した場合に相続人となるべき者をいう。以下同じ。)が、被相続人に対して虐待をし、若しくはこれに重大な侮辱を加えたとき、又は推定相続人にその他の著しい非行があったときは、被相続人は、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求することができる。
廃除ができるケースは以下のとおり決まっており
- 虐待がある場合
- 重大な侮辱があった場合
- その他著しい非行があった場合
以上のいずれかに該当する場合に、相続廃除の手続きをすることで、特定の人に相続させないとすることができるようになります。
あげられた要件はかなり過激な状態ですべての人が対象の制度とは言えません。
なぜなのでしょうか?
民法892条の大きなポイントとして、相続廃除をすることができる対象は遺留分がある推定相続人に限られている点があります。
つまり、相続廃除の対象は配偶者、直系卑属、直系尊属に限られおり、たとえ虐待があっても、兄弟姉妹を廃除の対象とすることはできません。兄弟姉妹には遺留分がないためです。(遺留分とは)
一見不合理な制度設計のようですが、これは兄弟姉妹についは「②遺言書を遺す」でご紹介する遺言書を遺す方法をとることで、相続の対象から完全に排除することができるためです。
つまり、相続廃除の最大のポイントは推定相続人に遺留分すら残させないという点にあります。
兄弟姉妹を除く相続人は遺留分は当然に持っている権利ですので、それまでも取り上げてしまう廃除という方法は、とても過激な制度であるといえます。
したがって相続廃除の根拠である民法892条の要件は虐待、重大な侮辱、著しい非行など限定的な状況でのみ利用できるよう設計されているのです。
その相続廃除についは、家庭裁判所に対して申立てを行う方法と遺言書による方法があります。
まず家庭裁判所に対する申立てですが、申し立てができるのは虐待などを受けている本人が行う必要があります。
申し立てを受けた家庭裁判所は、審判手続きで相続廃除の妥当性を考慮します。
虐待が確認できる具体的な証拠(虐待の事実がわかる音声、動画、医師からの診断書)があると良いです。
次に遺言による相続廃除の方法があります。
遺言書のなかで、推定相続人の相続廃除の意思表示をしておくと遺言の効力が生じた段階で「遺言執行者」が家庭裁判所に相続廃除請求の申立てを行います。
家庭裁判所が相続廃除を認める審判を出し、確定した場合相続廃除された相続人はさかのぼって相続権を失います。
生前に相続廃除を行うと虐待の程度が激しくなる可能性もあるため、その場合は虐待の証拠は遺しておき遺言による相続廃除が良いでしょう
記載すべき遺言書の内容ですが
第〇条
遺言者の長男A(年月日生)は遺言者に対し、顔を殴りつけるなど暴行を加える虐待をし、Aによる浪費から遺言者に金銭の要求をする、借金返済の肩代わりをさせるなど、著しい非行を続けたため、遺言者はAを廃除する。
などがあげられます。
相続廃除は先の説明のとおり、遺留分をも取り上げる制度であるため要件が限定的で活用はあまりされていない制度です。
②遺言書を遺す
遺言書を遺すことで法定相続分とはことなる内容の相続をすることができます。(法定相続分とは)
例として夫死亡、相続人が妻と子供2人とした場合の法定相続分は妻が4分の2、子供が4分の1ずつになりますが、妻にすべて相続させるとする内容の遺言書を作ることができます。
これにより、子供2人には実質的に夫の財産を相続させないとすることができます。
ここでの注意点は子供2人には法律上「遺留分」が認められていることがあります。(遺留分とは)
このケースでの遺留分は(法定相続分)×(遺留分割合)×(1/子供の人数)です。
つまり子供にはそれぞれ(1/2)×(1/2)×(1/2)=(1/8)ずつ遺留分が認められます。
遺留分は遺言書で子供に相続させないとしていても、相続人である子供に当然に認められる権利です。
この遺留分すら認めたくない場合は、先の廃除をする方法をとる必要があります。
なお兄弟姉妹についての遺留分は認められておりませんので、単に遺言書で兄弟には相続させないとする内容のものを遺せば問題ありません。
先のケースの記載すべき遺言書の内容ですが
第〇条
遺言者は、遺言者の有する【財産の記載】を含む一切の財産を、遺言者の妻X(年月日生、住所:〇〇〇)に相続させる。
第〇条(付言事項)
【妻に全財産を相続させたいとする理由】であるから、子供であるY、Zは遺留分侵害額請求を行使するなどの紛争を起こさないようにしてほしいと願っております。
などがあげられます。
相続廃除をせずに妻に全財産を相続させるとすると、子供の遺留分については付言事項としてお願い事になってしまう点が注意点です。
以上、この人には相続させたくありません!相続人に相続させない方法でした。
司法書士杉並第一事務所では、遺言書の作成支援を行っております。
ご連絡は下記の電話番号またはお問い合わせフォーム、各種SNSよりうけたまわっております。
お読みいただきありがとうございました。